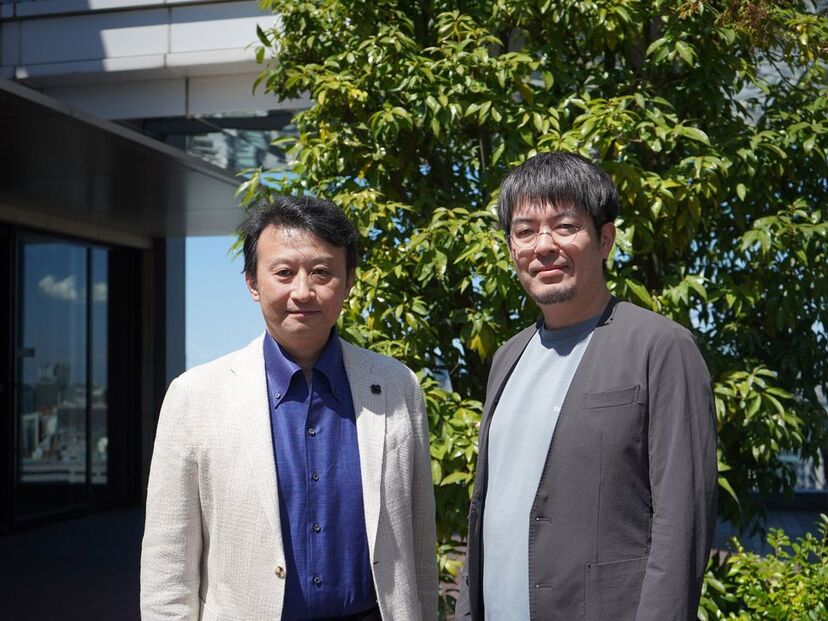【社会】オタクの知識が日本の安全保障のカギになる…軍事研究のプロ2人が異色の「会いに行ける情報機関」を作ったワケ
【社会】オタクの知識が日本の安全保障のカギになる…軍事研究のプロ2人が異色の「会いに行ける情報機関」を作ったワケ
■あっという間に4000万円が集まったクラファンの中身
――お二人が設立した民間インテリジェンス組織DEEP DIVE。設立費用として当初1000万円を目標としていたクラウドファンディングは、2カ月で支援者2933人、支援総額4232万5659円に達しました。
【小泉】想像以上に皆さんから期待していただいているなと感じています。クラウドファンディングサービスを提供しているキャンプファイヤーの担当者さんと最初に話したときには「800万円くらいかな」と言っていました。ただ私が「ツイッターのフォロワーが20万人います」と言ったら、急に向こうの目の色が変わって(笑)。
結果的に、目標額の400%を達成し、しかも2933人もの人たちが、我々の活動、掲げた理念に共鳴してくれたことに深く感謝しています。
【小原】まずは小泉さんと二人で、自分たちのできる範囲で立ち上げようと。そこで広く呼び掛けて、ご協力いただけたらという思いで始めたところなので、多くの方がその呼びかけに応えてくださったことが大変ありがたいですし、ご支援いただいた資金で基盤をしっかり作って、これからの活動が継続できるようにしていかなければと思っています。
――設立の目的として、〈デジタル公開情報インテリジェンス(OSINT)と衛星情報インテリジェンスにより、日本社会にとって必要な警告をいち早く届ける〉とあります。
【小原】公開情報と衛星情報を使うのは、「明確な根拠を示す」ということで、これはインテリジェンス機関としては新しいのではないかと思っています。
私たちもテレビなどで台湾有事などについてコメントをしますが、短い時間しかなく、なぜそのようなコメントをするに至ったかの根拠を示すことができないことが多くあります。
そこでDEEP DIVEでは、インテリジェンス機関として分析に使った衛星画像などを公開し、根拠を示す形で情報提供していこうと考えています。根拠を示せば、「違う」と思う人がいれば反論することもできますからね。
■多くの人の知見が必要なワケ
【小泉】インテリジェンスにも反証可能性が必要だと思っていて、例えば「アメリカの高官がこう言っている」「某国のインテリジェンス機関によると……」というものでは、誰にも検証できないわけです。「信じるか信じないかはあなた次第です」という領域に入ってしまうので、そうではない、根拠のある分析であるか否かを、みんなで検証できる形のインテリジェンスを実施していこう、と。
【小原】「みんなで」というのがもう一つ、新しい点だと思っています。今までのシンクタンクでは、提言を出したりセミナーを開催したりはしますが、やや一方通行のものになりがちです。DEEP DIVEは議論のハブになりたいと考えていて、こちらが情報を出すだけでなく、それに対してどう考えるか、気づいたことはないか、などより多くの人の知見を得たいと考えています。
私や小泉さんは軍事や安全保障の観点から衛星画像を分析していますが、実はそれだけでは不十分です。違う知見を持った人たちによる分析が加わらなければ、本当の姿はなかなか見えてこない。
例えば先日も、ある衛星画像を見ていて不明な点があったので、建設会社の方に聞きに行ってきました。建造物についてはやはりその道のプロに聞くのが確かです。
■中国のウイグル地区にある謎の穴
【小原】以前から、中国分析をする人たちの間では「中国分析は『群盲象を撫でる』のようなものだ」と言われてきました。軍事だけ、共産党組織だけ、中国文化だけを見ていても全体像は分からない。そうした知見を持ち寄って分析することで、全体像が見えてくるのではないかという考えです。
――DEEP DIVEのサイトでは、「なんだかわからない中国のウイグル地区にある穴」の衛星画像が公開され、情報を募っていましたね。
【小原】記事公開後、かなり多くの情報や分析が届いています。ありがたいことに、記事公開以降、ウォッチし続けてくれている人もいるようです。
【小泉】オタク的な観点で記事を出すことで、誰か別のオタクが反応してくれる。それが議論のきっかけになるだけでもいいんです。まさに日本版「べリングキャット(※)」のように、その筋のオタクや、見た人が興味本位で調べたことがつながりネットワーク化していくことで、何らか分析や発見に行き当たる可能性がある。
※ 公開情報を分析するOSINT(オープンソース・インテリジェンス)の手法を使い、偽情報や誤情報の検証を続けている民間の調査報道集団
こうした形態は、公開情報を使って分析している民間組織だからできることです。情報を表に出せない国の機関とは違う、緩いつながり、グラデーション状の協力関係が作れるといいなと思っています。
■なぜ国からの情報だけではダメなのか
【小原】「ハブになる」ことの意味は、こうした専門知の持ち寄りの他に、さらに二つあります。
一つは政府や民間、政府と地方自治体など、政府と社会の間のハブになりたいという点です。
政府は秘匿された情報をたくさん持っていて、分析力も高い。ですから私たちは何もこれに対抗しようと思っているのではありません。
しかし、たくさん持っている情報はもちろん、「何がわかっていて何がわかっていないか」についても機密ですから、政府は公開することができません。政府内や日米間、あるいはGSOMIAのような協定を結んでいる国とは情報を共有したうえで議論できますが、それ以外の地方自治体や民間組織とは共有できないのです。
近年、地方自治体も有事の際の住民避難計画を作り始めてはいますが、いつ発動するのか、どの避難ルートを取るかというのは、情報がなければ判断できない。しかし国に対して「どうなっているのか」と問い合わせるだけでは、何も情報を出してもらえません。
自治体側も「こういう情報を持っているが、国としてはどう考えているか」と示して初めてやり取りができるようになる。DEEP DIVEはその情報を提供することで、ハブの役割を果たしたいのです。
■自国の安全保障を英語圏に頼る
【小泉】海外に駐在員を派遣している大手商社の人たちは「ストラトフォー」のような、アメリカの民間シンクタンク兼インテリジェンス機関が提供する地政学リスクに関するレポートを読んで危機管理に生かしているのですが、これはあくまでも英語圏のもの。これまで、我々自身のリスク管理の多くの部分を英語圏に頼ってきた面があります。
しかし、大規模な地政学リスクに日本が巻き込まれそうだという時に、日本の組織が早期警戒情報を発信できれば、その情報を地方自治体や民間組織が得たうえで、どういう行動を取るかの判断材料にできる。そういう情報を提供する日本の機関が必要です。
衛星情報は、お金を出せば買うことができます。なので、実はやるかやらないかはやる気の問題でしかない。だったらということで、日本ではまずDEEP DIVEが「自分でやります」と手を挙げました。
【小原】もう一つ、ハブになるというのは国同士の情報共有です。政府の情報は公開できませんが、私たちが使うのはオープンソースですから、広く知らしめて全く問題ない。衛星画像をもとに、国を超えて「今はこういう情勢だ」と共通認識を持つことができれば、議論もできます。しかしそれができないと、協力しますといったところで話の土台を共有することができません。
そこでDEEP DIVEでは、衛星情報をもとに、私たちのこれまで培ってきた蓄積と照らし合わせていく。それによって変化の兆候をつかむことができますから、「次はこうなるかもしれない」という警戒を発することもできるでしょう。
■なぜ自分たちで調べようとしないのか
【小原】すでに海外からのアプローチもあります。軍事・安全保障系の機関ではなく外交系の組織から情報共有をしたいという話が来ています。これはこれでとてもありがたいのですが、不満なところでもあります。我々は日本のために働きたいからこそ始めたことなので、まずは日本の組織に関心を持ってもらいたいですね。
――トランプ政権の発足で日米関係やアメリカの情報機関もどうなるか分からない中、日本の「自前」の情報機関の必要性は増していますね。
【小泉】これまでにもいろいろなところで話してきたのですが、2017年の北朝鮮によるミサイル危機の際には日本も大騒ぎしたものの、その実、語られていたのはアメリカの情報機関や研究所、シンクタンクの見立てばかりでした。「なぜ自分たちで調べようとしないのだろう」と不思議でならなかったんです。そんなに問題なら自分たちでやればいいし、資金さえあれば手に入る情報もある。
もちろん政府はやっていると思いますが、日本の研究機関、日本人が自分たちで分析して、議論していくことが大事ではないか。やれるんだということを示したい気持ちがありました。
【小原】他国の情報に頼ると、その国の意向によって出てくる情報が制限されたり、ひどい時には情報が偏向する可能性さえあります。その国にとって都合の悪い情報が出てこないこともある。
■ウクライナ戦争を予期できなかった反省
【小原】アメリカのシンクタンクは政権の意向を受けてレポートを書くこともありますが、実は日本の省庁が予算を付けて、アメリカのシンクタンクに「こういうレポートを出してください」と依頼することすらある。以前から、なぜ日本の組織に頼まないのかと不思議に思っていました。
――「アメリカがこう言っている」という威光が欲しいんでしょうか。
【小泉】ちょうどいいときに、ちょうどいい感じの外圧が欲しい、ということなのでしょう(笑)。
日本の場合は、地域研究は他国と比べても分厚くて、これだけやっている国は他に中国くらいではないかというほど、安全保障に関して多くの知見を蓄積しています。ただあくまでもアカデミックなものであり、いざという時にアーリーウォーニング(早期警戒)を鳴らせるインテリジェンスとはタイムスパンが異なります。
私も一ロシア軍事屋として反省しているのは、日本のロシア専門コミュニティが、2022年のウクライナ戦争を予期できなかったことで、むしろ「やるわけないだろう」という意見が大半でした。これはアカデミックな知が扱っているタイムスパンが、インテリジェンスの観点とは異なっていたからでしょう。
■使える情報をドンドン出していく
住民避難や駐在員の引き揚げといった、その時、直ちに判断しなければならないようなケースにおいて、民間が判断材料にできるもの、活用できる資源は多くありません。そうしたものをDEEP DIVEが提供したい。
以前であれば軍事機密だった、地上から発信する外国の発射するレーダー波・ミサイル誘導電波などを受け取って位置情報を特定するようなデータも、お金を払えば得られるものになっています。「やる気の問題」というのはそういうことです。
【小原】私は自衛隊を退職した後、イギリスのジェーンズ(アメリカの企業IHS傘下)という機関に所属していましたが、日本政府をはじめ、多くの企業などがジェーンズからレポートを購入し、リスク管理に使っていました。「なぜ海外のシンクタンクに頼るのか」と聞くと、「日本には使える情報がないからだ」と言われたことを今でも覚えています。
使えるものがないなら、自分たちでやろう、と。我々は自治体や民間組織の行動を判断するために「使える」情報を出したいと考えています。
先ほど小泉さんがおっしゃったように、電波情報などから分析するエリント(ELINT、電子収集情報)や、シギント(SIGINT、通信傍受情報)などの一部は、民間機関でもお金を出せば得られます。民間組織でも、オープンソースを使ってでもやれることはあるというところを見せたいですね。
■事務の大切さが身に染みた
【小泉】DEEP DIVEは非営利の一般社団法人ですが、分析した情報をリスク管理に使っていただく、そういうビジネスモデルを回していく枠組みを作らなければなりません。まずは最初の一年が勝負だと思っていますが、4月7日にすでに発表されたように、東京海上ディーアール株式会社のリスクマネジメント部との業務提携協定が発行されました。
そして足場固めのこの一年の活動をするための資金は、皆さまにご支援いただくことができました。本当にいいスタートを切れたと思います。
【小原】今は私と小泉さんの二人しかいないので、事務を回すのに四苦八苦していますが……(笑)。先方から「請求書を出してください」と言われてもこれまで一度も書いたことがないですし、法人口座を開設するだけでも一苦労でした。
【小泉】軍隊もそうですが、バックヤードや広義のロジスティックがうまく行っていないと、組織は回らない。東浩紀さんの『ゲンロン戦記』(中公ラクレ)を組織経営の教科書にして、これから事務担当者の採用など組織づくりを進めていきたいです。
■期待のウラにある危機感
――期待は大きいですね。
【小泉】やろうとしていることは、住民避難の早期警戒情報を出すなど、警告を発するものですから、楽しい話ではなくて、むしろヤバいことが起きそうなときに、その兆候を知らせるというものです。そこに期待している人たちは、現在の安全保障環境に強い危機感を持っています。
一方で、支援と同時にいただいた多くのメッセージには、怖い、不安だという後ろ向きなことだけではなくて、「何か新しいことをやってくれるなら応援したい」という激励や、「そこに自分も何らかの形でかかわりたい」というものもありました。
DEEP DIVEにあるのは、「みんなでやる安全保障」という観点です。安全保障の話は国家がやるものであるとか、右や左の対立から語られてしまうと、多くの人にとっては「どこか遠いもの」になってしまいがちです。でも自分たちが安全保障の当事者となって、何かやってみたらどうなるのか。
ご支援いただいた方は、みなさん安全保障の「一口株主」になるような感覚があるかもしれません。自分もそこに、何らかの形で関与していたいというような思いを持ってくださっています。
■いわば「会いに行ける情報機関」
【小泉】実は本来、国家安全保障ってそういうものなんですよね。国家の安全保障も自分たちが払った税金でやっていることですから、その意味で実は納税者はみんな「一口株主」なんですが、国家安全保障というとやはり遠いものに感じられる。
その点、DEEP DIVEは「ネットでつながっている、近い人たち」がやっていて、しかも僕たち私たちも3000円からのお金を払って参加している、というような感覚で応援してくださっている。その親近感は大事にしたいです。
【小原】セミナーや交流の場、会員としてDEEP DIVEに長くかかわっていただけるような仕組みも作る予定です。
【小泉】いわば「会いに行ける情報機関」というところでしょうか(笑)。
【小原】そうですね。せっかく株主になっていただいた以上は、ぜひ「物言う株主」になって、あれこれご意見いただければと思います。
———-
笹川平和財団上席フェロー
各種メディアで情報発信している安全保障、中国の軍事問題の専門家。1985年防衛大学校卒業、1998年筑波大学大学院修了。1985年海上自衛隊入隊後、回転翼操縦士として勤務。2003~06年駐中国防衛駐在官。2006年防衛省海上幕僚監部情報班長、2009年第21航空隊司令、2011年IHS Jane’sアナリスト兼ビジネス・デベロップメント・マネージャー、2013年東京財団研究員を経て、2017年から笹川平和財団上席研究員。著書に、『中国の軍事戦略』(東洋経済新報社)、『世界を威嚇する軍事大国・中国の正体』(徳間書店)、『何が戦争を止めるのか』(ディスカバー・トゥエンティワン)などがある。
———-
———-
東京大学先端科学技術研究センター准教授
1982年、千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー文芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』(ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)などがある。
———-
———-
ライター・編集者
1980年埼玉県生まれ、中央大学卒業。IT企業勤務の後、月刊『WiLL』、月刊『Hanada』編集部を経て現在はフリー。雑誌やウェブサイトへの寄稿のほか、書籍編集などを手掛ける。
———-