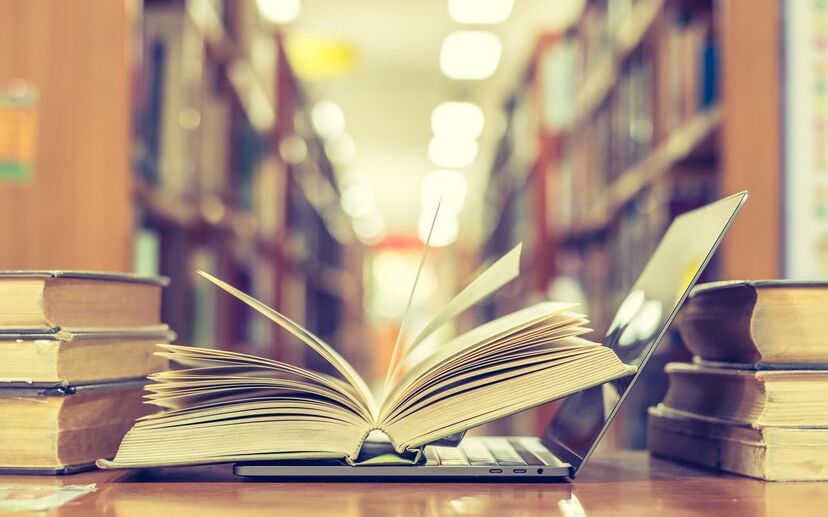【社会】「大学教授は雑務に追われて研究時間がないから」は疑わしい…日本の研究力が落ちている”意外な理由”
【社会】「大学教授は雑務に追われて研究時間がないから」は疑わしい…日本の研究力が落ちている”意外な理由”
※本稿は、竹中亨『大学改革 自律するドイツ、つまずく日本』(中公新書)の一部を再編集したものです。
■ドイツの大学における内部任用の禁止
人事のあり方も自己規律との関連で興味深い。大学にとって人材の質は生命である。いくら研究設備が最新鋭であっても、優秀な研究者がいなければ宝のもち腐れである。だから、どの大学も優れた研究者を教授に獲得すべく、人事には最大の努力をはらう。
大学の人事は外部からは見えにくい面がある。人選の条件はポストごとに異なるし、さらに教育・研究の内容は専門的だから、最善の人材が教授に選ばれたのかどうかは外からは判断しにくい。そこで、外部の目が届きにくいのをよいことに、仲間うちの馴れあいに流れる危険が生じる。馴れあいを排し、質を最優先した人事選考をいかにして可能にするか。そこでも鍵になるのは自己規律である。
ドイツではこの点、古くから手立てが講じられてきた。有名なものは内部任用の禁止である。これは、教授任用は必ず外部からに限るという原則であり、たとえばその大学にすでに助手として在籍する者は、いかに優れていても教授候補にはなれない。内部任用禁止は法律にも規定があり、自己規律とばかりはいえないが、慣行として確立している。
■厳格で入念なドイツの教授任用の手続き
ドイツの教授任用の手続きはかなり厳格で入念である。大学等で聴取したところをまとめると、おおよそ以下の手順である。なお、これは通常の任期なし雇用の教授職についての手順であり、任期付きの助教授の任用法はこれと異なる。
まず人事が始まるにあたって、そのポストがひきつづき当該学部に与えられるか、さらにそのポストで行われるべき教育・研究活動に変更はないかなどについて、参事会の承認が必要である。言いかえれば、現任者が辞めたからすぐ空きを埋める、とはならない。
参事会でゴーサインが出て人事開始となるが、それからが結構長い。任用手順が完了するまで最短でも1年半はかかる。加えて、後で述べるように、選考の過程では学内の他部署から種々のチェックが入る。もし、何らかの疑義が出され、その結果手順を繰りかえすことになれば、その分選考は長びく。2年、3年とかかることは珍しくない。
正式な手順が始まる前に準備的な作業を行うこともある。たとえばマックス・プランク協会は、専従のスカウト担当職員を使って、退職予定の教授ポストの候補者を数年前から国際的に物色する体制をとっている。
■人事は必ず国際公募による
さて、選考の主体となるのは、その都度組織される人事委員会である。その規模は総勢10人ほどで、主体となるのは関係する専門分野の教授である。それ以外に学部長、全学の参事会からの代表、学内の共同参画推進部門の代表なども加わる。また、必ず学外からも1、2名のメンバーを選ぶ。委員会の規模が大きい一因は、人事は必ず国際公募によるためである。有名大学では国内外からかなりの数の応募があるので、選考を進めるうえで人手がいる。
選考方式は多面的である。まず、委員会で応募者の提出した書類や研究業績などを審査する。そのうえで、候補を有望な数人に絞りこみ、本選考に移る。本選考では、有望候補者は人事委員会の面接を受けるとともに、学内に対して広く自らをアピールする。すなわち、公開の場で教育・研究についての抱負を開陳し、講演によって自らの研究を紹介して聴衆からの質疑に答える。また、学生相手に模擬授業をも行う。これと並行して、人事委員会は外部の専門家に有望候補者についての所見を求める。
以上の手順を経て、委員会は選考結果として最終候補者リストを作成する。最良と見る候補者を3人程度、推薦順位をつけて挙げたものである。リストは学部の教授会、さらに参事会へと回付される。それぞれの場で選考経過の是非が検討され、候補者の良否が審議される。多方面からの多重のチェックが入るわけである。そして最終的な判断を下すのは学長である。
学長は最終リストから、自らが最適と考える候補者を選ぶ。その際、人事委員会の推薦順位は勘案しなくてよい。さらに場合によっては、どの候補者も学長の眼鏡にかなわないことがある。その場合、人事は振り出しに戻る。
■たいへんな時間と労力を要する手順
選考の手続きはこれで終了するが、ついでに述べておくと、任用が確定するまでにはもう一幕ある。選ばれた候補者との間で大学は任用交渉に入る。俸給や手当、さらには研究室の予算・設備、秘書の数などが折衝の的である。もし、候補者が大学の提示する条件に納得できなければ、この任用話は流れる。人事は振り出しである。
以上が、教授の新規任用の際の手順である。なお、ドイツの大学教授職には職掌や俸給で区別のあるW2とW3という二つの格がある(図表1)が、W2からW3への昇任についても内部任用禁止に近い、かなり強い制限がある。
これほど周到な手順をふめば、たしかに内輪の馴れあいの働く余地は小さかろうと納得させられる。他方、たいへんな時間と労力を要するのも事実で、ドイツの大学の友人も負担の大きさをこぼしていた。だが、だからといって選考手続きを簡略化すべきだという声はないらしい。人事の手間暇を惜しまないという自己規律が結局は大学の将来を担保するという認識が、関係者の間で浸透しているのである。
■人事はほとんどが「空きを埋める」もの
さて、わが国の国立大学の場合、かつてはよく閉鎖的な人事による学閥の弊が指摘された。
その後、改善が進んだのは事実である。それでも人事選考がドイツほど厳格かどうか、筆者には少なからず疑問である。
むろん、筆者は国立大学全般の状況を把握しているわけではない。人事の慣行は専門分野、大学や学部によって実にさまざまで、表向きの手順・手続きはともかく、実態はインサイダーにならないとわからない。その点、筆者の経験はきわめて限られている。とはいえ、10も20もの職場に勤めるのはだれにとっても無理な話だから、人文系での個人的経験をもとに、という但し書き付きで、筆者の見解を述べても許されよう。
筆者が大学を離れて以降、変化もあろうが、少なくとも当時は万事ゆるやかであった。まず人事はほとんど「補充人事」で、現任者が定年等で退職した後の「空きを埋める」ものであった。逆にいえば、ポストの存在自体は自明視されていて、ポストの配置や教育・研究の内容を見直すという話はほとんど聞かれなかった。
そのせいか、人文系では学科や専攻の新陳代謝が比較的鈍い。たとえば、各地の大学の文学部には、戦前以来の仏文、独文の学科を抱えるところが見られる。一方、たとえば東南アジア諸国やアラブ圏の文学を学ぶ学科や専攻を置いているところはきわめて少ない。
■人事をゆるやかにすれば人材の質に響く
手順は何につけ、簡素であった。選考は通例、学年初に始まって、秋には実質的には終了していた。人事委員会は3名程度と小規模であった。当時すでに人事はすべて公募による決まりだったが、ただ委員会が選んだ最終候補者は不思議に内部の者が多かった。つまり、教授が定年退職した後の人事で、そこの准教授が最終候補者となっているケースである。人事委員会の選考結果は、学部の教授会からさらに大学本部へと回されて承認を受けるが、筆者は寡聞にして、その過程で委員会の結論が却下されたという話は聞いたことがない。
人事をめぐって学部内で波風が立つのは避けたいと思うのは人情である。だが、そうした内輪の論理を優先させれば、長期にわたるツケとなりかねない。いったん採用された教授は、通例定年まで在職するからである。
ドイツの大学が人事を厳格かつ入念に行うのは、優秀な人材を確保したいためである。逆に、人事をゆるやかにすれば当然、人材の質に響くだろう。さて、日本の大学はどうだろうか。
■日独の研究者の格差には無視できないものがある
筆者は(本書で)すでに述べたような研究歴から、日本とドイツなどヨーロッパの人文系の教授の仕事ぶりについて、それなりに承知していると自負している。残念ながら、大学教授の質に関する彼我の格差には無視できないものがあると言わざるをえない。
たとえば研究業績を見ればよい。ドイツでは――若いころの留学時代にミュンヘン大学の恩師から聞かされた話だが――有力大学の教授に招聘されるには、最低でも3冊の著書が要る。まず、研究者としての出発点である博士論文である。次が教授資格論文である。これは、研究者としての幅を広げるため、博士論文とは異なるテーマで書くことになっている。双方ともそれぞれ数百頁程度の専門書である。そして3冊目が、いくぶん巨視的なテーマを扱った著書である。
一方、わが国の人文系の教授の間では、まとまった著書を全然もたない者もそう珍しくはない。さらに加えて、筆者の在職時には博士学位をもたない教授すら結構見られた。ずいぶん以前には、人文系では博士号は教授として功成り名遂げた後にとるものという慣行があったが、筆者世代ではすでに学術研究の入口資格になっている。だから、ずいぶん面妖な話である。それに大学としての人事方針も問われよう。博士号のない教授を任用するという人事には、ドイツならまちがいなく参事会なり学長なりから制止が入る。
■ドイツは大学の教員構成がきわめてピラミッド的
もっとも、若干注意しておきたいのは、ドイツでは日本と違って、大学の教員構成がきわめてピラミッド的だという点である。先にもふれたが、教授の数は少なく、助教授を合わせても全大学教員の12パーセントにしかならない(Hüther/Krücken 2018: loc. 1966)。大多数をなすのは、「学術職員」とよばれる非教授身分の教員(任期付き雇用の、いわゆるプレドクやポスドク)で、その他助手などがいる。一方、わが国の国立大学では教授と准教授を合わせた比率は60.1パーセントである(文科省 2024)。したがって、教授という肩書きだけで日独を単純に比べることはできない面はある。
ともかくも、これほど格差があれば、たとえばドイツの大学と国際交流をするといってもうまく進まない。研究者として対等な付き合いが不可能だからである。加えて、言語面の格差もある。ドイツにかぎらずヨーロッパ諸国では、研究者なら普通、英語による意思疎通ができる。日本学研究者の場合、ほとんどの者がこれに加えて日本語を流暢に操る。残念ながら、同じことは日本側の人文系研究者には必ずしもあてはまらない。
■英語不要論に安住してはいけない
もっとも、日本文学や日本史などを中心に、これに反駁して英語不要論を唱える向きもあるかもしれない。日本研究のリンガフランカは日本語なのだから、国際的な舞台でも英語など必要ないというのである。これは危うい議論である。筆者の見るところ、欧米の日本学研究者にとって、日本語はいわばフィールドワークのツールにすぎない。文献や資料を読み、現地調査するのに日本語は必要である。だが、論文発表や学会報告などアカデミックな活動となると、用いられるのは英語である。英語不要論に安住していると、日本研究の国際的な言論空間から排除されたままになりかねない。
■管理業務が増える傾向はドイツも同じ
あるいはまた、ドイツとは違って日本では、教授は雑務に追われて研究時間がないから、という声があがってきそうである。しかし、大学人の職務で管理業務が増える傾向にあるのはドイツとて事情は同じである。「教授の仕事が教育・研究だったのは昔の話、今は教育・研究マネジメントが仕事」という自嘲の声があるやに聞く。さらに加えて、ドイツの大学での教育負担は国際的に見て高いという定評がある。
というわけで、ドイツの大学教授が勤務時間のうち研究にさけるのは20.8パーセントにすぎない。助教授でも26.2パーセントにとどまる(Fabian et al. 2024: 14)。ちなみに、わが国の大学教員は32.9パーセントを研究にさいている(文科省 2023: 15)。
昨今、わが国の研究力凋落について議論が盛んだが、研究者の質における格差も勘案する必要がありそうである。理系では国際的通用性が高いだけに事情は異なろうが、人文系などについては看過できまいと考える。
———-
大学改革支援・学位授与機構教授
1955年大阪府生まれ。83年京都大学大学院文学研究科博士後期課程退学。東海大学助教授などを経て、93年より大阪大学助教授、2000年より教授。博士(文学)。著書『ジーメンスと明治日本』(東海大学出版会、1991)『近代ドイツにおける復古と改革 第二帝政期の農民運動と反近代主義』(晃洋書房、1996)『帰依する世紀末 ドイツ近代の原理主義者群像』(ミネルヴァ書房、2004)『明治のワーグナー・ブーム 近代日本の音楽移転』(中公叢書、2016)『ヴィルヘルム2世 ドイツ帝国と命運を共にした「国民皇帝」』(中公新書、2018)など。
———-