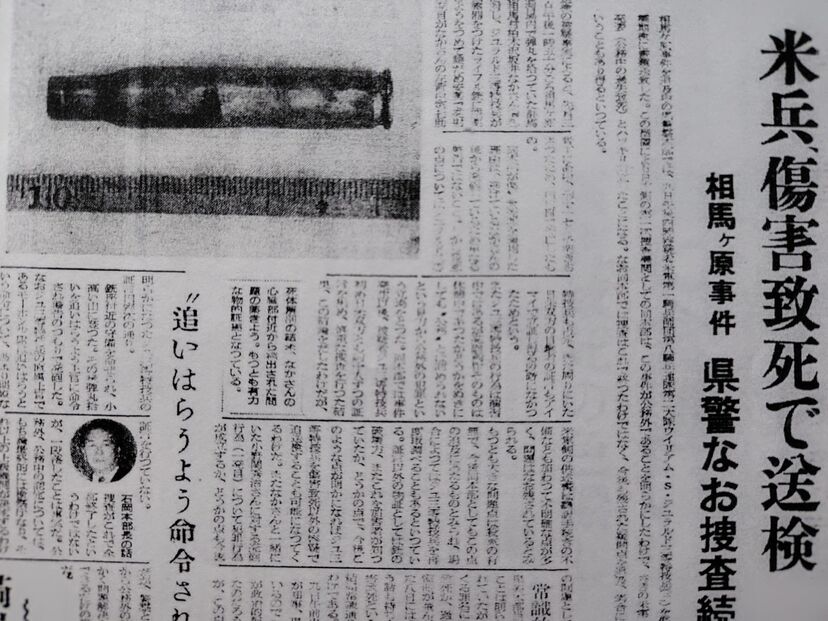【社会】「日本の女を狙い撃ち」「生きている人間をマトに」群馬で起きた殺人事件が日米を揺るがせ…68年前に残されていた“怒りの声”
【社会】「日本の女を狙い撃ち」「生きている人間をマトに」群馬で起きた殺人事件が日米を揺るがせ…68年前に残されていた“怒りの声”
〈「ママサン、ダイジョウビ」21歳アメリカ人男性が日本人主婦(46)を後ろから…国際問題に発展した“世紀の事件”のゆくえ〉から続く
1957(昭和32)年の1月に起きた「ジラード事件」。群馬県の演習場で21歳のアメリカ兵ウィリアム・S・ジラードが、弾拾いに入り込んでいた46歳の農家の主婦・坂井なかさんを「ママサン、ダイジョウビ」とおびき寄せたうえ、後ろから撃ち殺した。国際問題に発展したこの事件は、いったいどのような結末を迎えたのか。
当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略する(全3回の2回目/はじめから読む)
◇◇◇
弾拾いをしなければ生きていけない
戦後の区域拡大の際に土地を強制接収された農家も多く、演習場は周辺住民に多大な影響を及ぼしていた。
茜ケ久保重光議員ら日本社会党調査団の現地入りを報じたのと同じ2月6日付上毛朝刊1面には「彈拾いをしなければ“生きていけない” 貧しさが生んだ悲劇? 立入禁止強化は困る “不安”と“動揺”の相馬村民 現地にみる」という記事が見える。ここには基地と“共生”しなければならない住民の本音が表れている。
〈 全国から注視のマトとなったはずの現地、群馬県相馬村は、村当局をはじめ村民たちが、こんなに問題が大きくなるとは思っていなかった(一村民の話)という表情を見せていた。
なかさんの位牌の前で夫・秋吉さん、目撃者の小野関英治さんの事情聴取が行われたが、警察、米軍、新聞と、質問や参考人調べで5日間を過ごしてきた2人はなんとなく口が重そうに見えた。同じ表情は近所の主婦たちにも見える。2人と秋吉さんの長男は次のように説明した。
「もし米軍から厳重に立ち入り禁止を通告されたら、村民の生活手段がなくなるのです。もう一つ不安なのは、ほとんどの村民が法律を破っているから、そんなことで調べられはしないかと思っています。でも『射殺されたんだ』という思いが皆にあり、あれやこれや、気持ちが複雑なので沈んでいるように見えるのです」〉
記事は弾拾いの実態に入っていく。
薬莢は10倍の値段に「ライフル銃の訓練は大歓迎」
〈 この弾拾いは戦後、空き缶拾いから始まり弾丸に移ってきたが、(日本が独立した)1952(昭和27)年ごろは組合があり、1カ所に回収して分配した。だが、弾拾いは早い者勝ちで、抜け駆けした方が収入が多いので、1954(昭和29)年ごろ、組合も消滅してしまった。
その後、「買い子」といって仕切り屋が高崎方面からトラックで来て買い集めるようになり、競争意識にさらに拍車がかかるようになった。そうしたことが今度の事故を招いたようだ。砲弾の破片で1貫(3.75キロ)当たり85~90円(現在の約470~520円)、薬莢だとその10倍の800~900円(約4700~5200円)になるので、事故の日のようにライフル銃の射撃訓練は大歓迎された。多い人は1日4貫目(15キロ)、3400~3500円(2万円前後)の収入とのこと。
実弾射撃訓練があれば、村の人たちはまた「立ち入ります」とのこと。それほど農閑期の村民にとっては弾拾いが必要になっている。そうしなければ生きられないのだ。〉
射殺された女性は8人家族
朝日も2月7日付朝刊で「『弾拾い』やめられぬ “生活の糧を失う”」という記事を掲載。坂井一家についても触れた。
〈 相馬ケ原演習場は榛名山の南側に広がる原野。ここで弾拾いを始めたのは大正9(1920)年、旧日本陸軍の演習場開設以来のこと。米軍接収後は、村民の副収入だった炭俵編みの材料であるカヤが実弾射撃でひどくやられたため、貧しい農家は副収入の道を弾拾いに求めた。
射殺された坂井なかさん一家は8人家族。大正9年、旧日本陸軍に土地を強制買収され、1町5反の耕作地が5反に減った。最近では生活はもっぱら弾拾いに頼っていた。同家のある地区ではほとんど全戸が弾拾いに出る。相馬村と隣の北群馬郡桃井村を合わせた300~400人の住民にとって、完全な正業となっており、安い日雇い仕事をやる者がいない。〉
2月10日付読売朝刊も「弾拾い」をまとめており、その中で弾拾いでの死傷者数について「宮城県王城寺原射撃場周辺では既に不発弾事故110件、死傷者136人に達している。全国では数百人を数える」とした。2月10日付上毛朝刊は、相馬ケ原で流れ弾や持ち帰った不発弾の事故での死傷者は29人。北富士、東富士、饗庭野(あいばの)各演習場を加えると150人以上に上ると書いている。
死亡事故のあとも弾拾いは続いていた
2月7日付朝日夕刊コラム「三角点」はこう嘆いた。「土地を取り上げられ、弾拾いに行けば殺される。命は一体どこへ拾いに行けばいいんだ」。生活に苦しむ住民が置かれた立場は際どかったが、実際の弾拾いはさらに際どく危険な作業だった。2月7日付朝日朝刊の記事は続く。
〈 演習が激しくなるほど弾拾いも忙しくなるわけで、最近では、発砲しながら突撃演習をする米兵部隊に“従軍”。手袋をして発砲直後の弾き出された熱い薬莢を争って拾う。実弾射撃の中をかいくぐり、中には砲弾の着弾点近くにタコツボを掘り、爆発を待つ者さえあった。当然犠牲者が出るわけで、1月の桃井村の死亡事故の際も、村民は「運が悪かった」と諦め、弾拾いは続けられていた。〉
事件当日も現場付近には約50人の弾拾いの日本人がおり、危険だとして、午前中の実弾射撃訓練から午後は空包に切り替えたほどだった。
坂井なかさんを死亡させたのが空薬莢だったことについて、2月10日付朝日朝刊の「声」欄に、警察予備隊(のちの自衛隊)で各種兵器の性能、扱い方の教育を受けたという人物が「薬キョウ発射も実弾の威力」という投書をしている。
ライフル銃などに空包を詰め、銃口に擲弾筒(細長い手榴弾)を付けて発砲すると、100メートル以上飛ぶ。銃口に密着する薬莢を差し込むことは発射ガスの威力を異常に強くし、押し出された薬莢は実弾と変わらない威力を持つという。
後で判明することだが、撃ったアメリカ兵は当日、自分の銃の故障で、普段は持てないグレネード・ランチャー(擲弾等発射装置)付きのライフルを上官から貸与されていた。そこに近くに落ちていた薬莢を逆さまに差し込んで発射したわけだが、おそらく、そうしたことは兵士の間で遊びとして日常的に行われていたのだろう。
「圧力で殺人を傷害致死に」
2月4日、茜ケ久保代議士は衆院内閣委員会で事件を取り上げ、「米兵は犬や猫に餌を与えるようにして撃ち殺した」と非難。真相究明を求めた。社会党は政府に徹底調査を申し入れる一方、現地調査に入ることを決定。問題は全国に知られることになった。社会党は以後も事件追及に積極的で、それがアメリカ側の対応にも影響を与える。
内閣委の報道と同じ5日付朝刊で上毛は米軍三ケ尻キャンプのウエリントン地区司令部民事部長レイカス大尉にインタビュー。「事故は被害者が立ち入り禁止区域に入ったために起きた。兵の行為は立ち退かせるためで、正規の演習中の出来事だから公務だと思う。殺意は認められず、公務上の過失致死と考えている」との見解を引き出した。同大尉は6日、群馬県知事と面会。第一騎兵師団長から遺族への哀悼の意を伝える一方、立ち入り禁止区域の周知徹底を求める書簡を手渡した(2月6日付上毛夕刊)。
さらに7日付朝刊各紙には、共同通信配信と思われる6日発表の第一騎兵師団の声明が載った。「演習中、銃座正面にいた一部の日本人市民に警告のため、一兵士が空包に薬莢を詰めて空中に向けて撃ったものらしい」という内容で、米軍の公式見解として物議を醸すことになる。この後、アメリカ側の態度は微妙に揺れるが、「公務中だから裁判権はこちらに」という基本的な姿勢は最後まで変わらなかった。8日には公務証明書が発給された。
「県警や地検は米兵の氏名の公表を拒否している」(5日付朝日朝刊)とされたが、同日付毎日夕刊は、前橋地検から法務省に入った連絡として氏名を報じた。しかし、「ジラード・S・ウイリアムス三等特技兵(21)」と姓名を逆に記載。しばらくこの表記を続ける。
翌6日付朝刊で上毛は「ウイリアム・S・ジュラルド」とした。以後も「ジラルド」の表記が各紙で続く。「三等特技兵」は「上等兵と曹長の間の階級」といわれ、「兵」と言っても正確には最下位の下士官のようで、後でそう表記を変えた新聞もある。
弾拾いを「恥ずかしい」とする見方も
2月6日付で毎日は初の社説「米兵の不祥事件を根絶せよ」を掲載。占領期を踏まえて「日本人に人命尊重を『教えた』はずの米国側によって、人命軽視を実地教育されるような事件が日本国内で起きるのは恐るべき皮肉」として徹底的な防止策を求めた。
半面、米軍責任者に厳重な軍紀を要望する一方、「命知らずのタマ拾いが出没し、爆発する砲弾へ突進するため、負傷・落命事故がしばしば起こる。こうまでして稼ぐ者の悲しさはさることながら……」とも指摘した。立ち入り禁止区域での弾拾いを「さもしい」「恥ずかしい」とする感情は日本人の中にも広くあったようで、早くも2月3日付読売夕刊1面コラム「よみうり寸評」では「日本人の貧しさをむき出しにした悲しい風景」と書いていた。
その後も評論家の臼井吉見は「もともと立入禁止を犯してのタマ拾いは、盗みにほかならない。割のいい現金収入の魅力が、彼らを駆って、公然たる盗みに赴かしめたのである」=「ジラード事件の教えるもの」(『現代教養全集第1(戦後の社会)』1958年)所収=と冷徹に批評した。
「日本の女を狙い撃ちに」「生きている人間をマトにして…」
対して2月7日付読売朝刊「編集手帳」は激烈だった。「日本の女を狙い撃ちにして殺した」「生きている人間をマトにして、クレー射撃の練習をするために日本に駐留しているとカン違いをしているらしい」……。
一方、地元の態度は微妙だった。2月8日付朝日夕刊に「『弾拾い』禁止せぬ 基地反対運動も拒否 相馬村村議ら」という記事が見える。
〈 相馬村では2月7日午後、村議、地区連絡員の協議会を開き、社会党群馬県連から申し入れのあった基地反対運動への協力を拒否することを決め、8日、回答した。村としては、基地撤廃が事実上不可能だとの空気が強いことと、政治的に利用されたくないとの理由から拒否に決定。協議会でも基地反対の声は全く出なかったという。また、弾拾いの演習場立ち入りについても、村としてはこれまで以上に強く禁止策をとることはできないとし、警察当局に一切を任せることを申し合わせた。〉
上毛も翌9日付朝刊「社会党の協力断る 生活の方が大切 政治闘争を恐れる村民」の見出しの記事を1面トップで伝えた。相馬村はこのころ、難題を抱えていた。事件現場を含む広馬場地区が桃井村(現榛東村)に、残りの柏木沢地区が箕郷町(現高崎市)に編入される分村の期日が近づいており、村民の関心はそちらに向いていた。分村は事件2カ月後の3月30日に実施される。
群馬県警は書類送検に向けて協議を進め、各紙はそれを報じた。2月9日付夕刊は上毛が「被疑事実は過失致死の線が濃いようだが」と書いたのに対し、読売は微妙な書き方だ。
〈 相馬ケ原事件を捜査中の群馬県警本部は8日夜、米軍捜査当局と交換した捜査資料のうち、銃の性能などを検討した結果、傷害致死容疑で進む事件処理方針を殺人及び殺人未遂容疑に切り替え、米軍第8騎兵連隊第2大隊、ウィリアム・S・「ジラルド」三等特技兵(21)の書類を送ることに決めた。だが、9日午後1時に来県した関東管区警察局・養老公安部長を迎え、石岡県警本部長らと再協議の結果、方針を再変更。従前通りの傷害致死容疑の方針で臨む態度を明らかにし、同日午後3時、前橋地検に送致した。〉
他紙も殺人から傷害致死へ方針転換したと書いた。『米兵犯罪と日米密約』によれば、県警内部では「国民感情を考慮に入れ、強気に出て故意による殺人罪で」で一致していたが、警察庁からの圧力があって傷害致死に変更したという。
9日午前には福田赳夫、中曽根康弘(いずれものち首相)ら地元選出の自民党議員団が県警を訪問しており、同書は「政治的判断があったと疑いたくなる」としている。10日付上毛は「常識的な線」としたが、事件を素直に見れば、殺意を認めるのは難しいが、米兵らは空包で薬莢を飛ばした場合の威力は熟知していたと思われ、殺人で立件する意味はあったと思える。
「殺意はなかった」と供述。目撃者の証言との食い違いも
2月11日の実地検証でジラードは「人に向けて撃ったが、殺意はなかった」と供述。発砲した際のなかさんとの距離については、日本人目撃者が7~10メートルと証言したのに対し「15~20メートル」と主張。食い違いを見せた。
2月15日付読売朝刊は、最高検が14日、前橋地検検事正と担当検事を上京させて首脳部会議を開いて協議した結果、事件は公務外の犯罪で日本側に裁判権があるとの方針を決定したと報じた。15日には中村梅吉・法相が同様の方針を明言。対して米側は同日、これまで通り「公務中の事件で、裁判権は米軍にある」と回答。法務省は16日、外務省を通じて日米合同委員会開催を正式に申し入れた。ここから約3カ月間、問題は日米合同委で論議が展開されることになる。
2月20日、社会党系の全国軍事基地反対連絡会議が主催する「米兵の日本婦人射殺真相糾明国民大会」が東京・新橋で開かれ、身柄引き渡しを受けての日本での裁判と賠償措置を求める決議をした。
「窃盗中、射殺された」
〈米兵、日本側で裁判 相馬ケ原事件
米軍相馬ケ原演習場で弾拾いの日本婦人、坂井なかさんを射殺した容疑者、米軍のウィリアム・「ジラルド」三等特技下士官の裁判権について、16日の日米合同委員会で日本側の裁判に服することに決まった。〉
同年5月16日付朝日夕刊は社会面4段でこう報じた。『米兵犯罪と日米密約』によれば、日米合同委の刑事裁判権分科会で3月12日から計6回、話し合いが行われた。内容はいまも非公開だが、「ジラードは上官から機関銃などの監視を命じられた公務中に、警告の意味で薬莢を発射。それが薬莢拾いに侵入していた坂井なかに当たって死亡させた」というアメリカ側の主張に対して、日本側は「機関銃の監視と射撃は無関係」と反論。
〈 ジラードの負った任務とあの銃撃が結びつく蓋然性のかけらさえもアメリカ側の口舌からは伝わらない。それに比して、日本側の応答は、邦人目撃者のみならず、米兵たちから得た傍証で事件の全貌をほぼ把握しており、正鵠を射ていた(『米兵犯罪と日米密約』より)〉
アメリカ側が裁判権を主張し抜けなかったのは当然だった。ところが──。
ジラードの引き渡しを拒否
5月18日付上毛夕刊は1面トップで「ワシントン17日発UP共同」の「ジラルド引渡し拒否 米国防省が指令」を伝えた。「ウィルソン米国防長官は17日、極東米軍に対し、『相馬ケ原の日本婦人射殺事件について、ワシントンで完全な再検討が終わるまでは、被告ジラルド三等特技兵を日本に引き渡すな』と指令した」。
末尾には「ワシントンAP=共同」で「米議員、裁判権の再検討を要望」という記事が付いている。国防長官の指令はこうした、駐留先の国が自国の兵を裁くことに反対する議員たちの圧力と国内世論に配慮したものだと分かる。
〈 米共和党のフランク・ボウ議員は17日、ウイルソン国防長官に公開状を出し、米最高首脳は相馬ケ原の日本婦人射殺事件の裁判が日本側の手で行われることになったのを再検討するよう要望した。同議員はかねてから、海外にいる米軍人の裁判をその国の手に任せることに反対していたが、この公開状の中で次のように強調している。
勤務中の軍人に関する裁判権を米国側が持つことはたびたび保障されていたにもかかわらず、相馬ケ原事件は日本側に移された。新聞は、今度の事件が勤務中に起こったものだとハッキリ書いている。現地の指揮官がそのような妥協をするようでは軍の統制がとれなくなる。〉
ここからうかがえるのは、アメリカの新聞が正確な報道をしていなかったことだ。一方、前橋地検は18日午後10時35分、ジラードを傷害致死容疑で前橋地裁に起訴した。
19日付朝日朝刊は「米の動きに異例の断」の見出しで「起訴は今週末になる見通しだったが、米国防総省の言明に、裁判権問題がまた蒸し返されることを恐れ、既に日米合同委員会で決まった『日本側で裁判する方針』を維持するためとみられている」と書いた。
「日本の裁判認めるな」高まる米国の反日感情
アメリカの世論も高まっていた。5月21日付上毛朝刊は1面トップに共同電で「米に沸き起る反日感情 国務省の指令を非難」の見出しを立てた。
〈 相馬ケ原事件の「ジラルド」三等特技兵裁判権問題をめぐって、このところ、米国内に反日感情が急速に沸き起こっており、米議会内でもこの事件を徹底的に追及する動きさえある。米国内の各地の新聞も「ジラルド」事件を極めて重視し、この事件について日本から送られた米系通信社の報道を連日のように大々的に掲載しており、一部の新聞は「日本の婦人が殺害されたのは遺憾だ。
しかし、この婦人は立ち入り禁止区内にいたばかりでなく、米軍の物品を盗んでいたので、公務執行中の同特技兵はやむなくその責任を果たしたにすぎない。この事件に関する限り、日本側には裁判権はあり得ない」との社説を載せている。〉
各紙にはその後もアメリカの反応が大きく掲載された。「“日本の裁判認めるな” 米の世論強硬」(5月21日付朝日夕刊自社特派員電)、「抗議、全米に広がる」(同、読売自社特派員電)。同じ日付の毎日は「ジラード事件・米議会も強硬 “日本の裁判権”が不愉快」としたが、もう1本「岸訪米にも響く?」の脇見出しが目立つ。
なお、この毎日の記事が、それまで各紙が表記していた「相馬ケ原事件」から「ジラード事件」に変わった最初と思われる。
台湾では「のぞきを射殺」も無罪
日本の政治史上、有名な「2、3位連合」で自民党総裁に当選し首相となった石橋湛山は、病を得て就任からわずか40日後、ジラード事件発生翌日の1月31日に総裁選で敗れた岸信介外相を首相臨時代理に指名した。
2月25日に正式に首相に就任した岸は東南アジア歴訪に続いて、重要な日米首脳会談のための訪米を控えていた。そのカウンターパートであるアイゼンハワー大統領は5月22日、記者会見で「ジラード事件には注目している」と述べたうえ「アメリカの市民に誤った法の適用が行われないよう国務、国防総省とも努力している」と語った。事件は発足間もない岸内閣の外交・安全保障上の難問になっていた。
また、また、大統領の発言には「国務、国防省鋭く対立」(23日付読売夕刊自社特派員電)という事情があったとみられる。記事は「国務省側では、事件は公務(時間)中だが休憩中のもので、公務外で起きた事件との解釈をとり、日本側への引き渡しを支持する傾向にある印象を受ける。一方、国防総省はあくまで休憩も公務中という解釈をとり、米軍側、すなわち軍法会議に付すことを主張している」と指摘した。
事態は「日米とも対策に苦慮 政治問題化す」(24日付上毛朝刊)となったが、検察は「訴訟手続き進める」(23日付朝日朝刊)、「政府、当面は静観」(24日付読売朝刊)。それでもアメリカでの動きは続く。24日付朝日夕刊社会面には「UPI=共同」のベタ記事が。「ジラード三等特技兵の出身地であるイリノイ州議会は23日、ジラードの日本官憲への身柄引き渡しに反対する決議を行った」。
実はこのころ、海外に派遣されたアメリカ軍人の犯罪が問題になっていたのはジラード事件だけではなかった。5月25日付上毛朝刊には「裁判のやり直し要求 全市に戒嚴(厳)令布(し)く」という台北発UP=共同電が載っている。
これは「レイノルズ事件」と呼ばれ、ジラードの裁判権が日米合同委の議題になっていた1957年3月2日、台湾へのアメリカ軍事顧問団の一員であるレイノルズ軍曹が、妻の入浴を盗み見たとして中華民国の官吏の男を射殺した事件。アメリカと台湾の間で地位協定は締結されておらず、レイノルズはアメリカの軍事裁判で正当防衛が認められ、5月23日、無罪に。
これに憤激した台湾のデモ隊がアメリカ大使館を占拠するなどして騒いだ。5月27日付上毛朝刊はワシントン共同電の「アジア各地で嫌われる駐留米軍 米政府も頭悩ます」という記事を載せている。アメリカにとって、軍の駐留国との関係を悪化しかねない難題になっていた。(後編につづく)
〈46歳主婦を撃ち殺すも「ヒーロー」と…「これでは無罪と同じ」日本中が怒りに沸いたジラード事件の結末が“物語るもの”〉へ続く
(小池 新)